送料無料サービスの限界?!ネット通販の拡大で深刻化するドライバー不足
2018/03/30
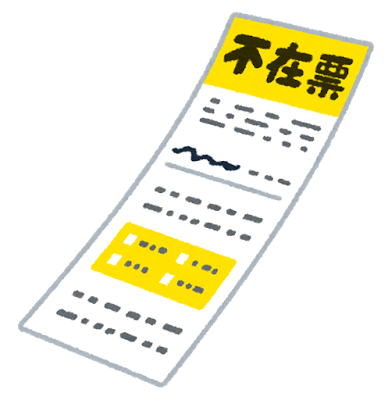
Amazonなどのネット通販・ネットショッピングの拡大で、ヤマト運輸のドライバー不足が深刻化しています。
再配達による労働環境悪化

問題視されているのは再配達です。
配達先が受取人不在で、1回目で受け取れない割合が20%といわれています。
たとえばせっかく30分かけて家に到着しても、無駄足に終わってしまうのです。
それでは効率の良い配達はできないですよね。
とくに利用者が家に帰宅してからの再配達依頼が多く、ドライバーの仕事が9時を回っても終わらないことが多いそうです。
休憩をとらずに10時間運転し続けたり、サービス残業を行う人も多いです。
残業時間は過労死ラインの80時間を超えるというドライバーがほとんどだそうです。
佐川急便のドライバーが受取人不在にイライラして荷物を何度も叩きつけた動画が話題になったのも記憶に新しいですね。
16年間ヤマト運輸で勤務してきたベテランドライバーが訴訟を起こしているというニュースも先日報道されていました。
毎月80時間のサービス残業を16年間続けてきたという訴えです。
慢性的に人手不足があり、サービス残業で不足分をカバーしてきたのが見えますね。
ドライバーの居眠り運転事故の報道も近年増えたように感じます。
私の知人のドライバーは居眠り防止のガムでは効果がなく、飲み物やパンをずっと食べ続けて眠りを我慢しているそうです。
ヤマト運輸は5年前に比べて社員を4000人増やして人手不足の解消に取り組んでいますが、新入社員が1日でやめたという話も聞きますので、人材の流出も激しいことが予測されます。
利益効率が悪い
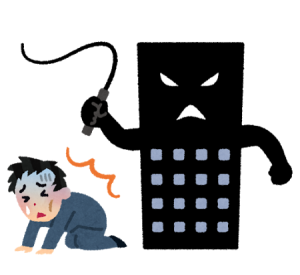
しかも、運送が増えれば利益が増えるかというとそうではありません。
その利益増加率は微々たるもので、圧倒的に手間の方が大きく割にあっていません。
運送業者の下請けも多く存在し、回しきれない荷物を別の運送会社に依頼しています。
その下請け企業がさらに下請け企業を利用し、3次4次の下請けが存在しているのが実情です。
どんどん下にいくにつれて利益はなくなっていきます。
下請け中小企業は仕事をきられるのが怖いので引き受けるといった関係になっています。
薄利をカバーするため少ない人数で多く荷物を運ばなければ会社の維持ができなくなっています。
これもドライバーの過労の原因のひとつでもあります。
増える送料無料

消費者の利便性を求めるあまり、送料無料の商品が多くなってきています。
1品から送料無料のものの大半は送料込での価格設定ですが、2500円以上買い上げで送料無料というところもあり、まとめ買いの場合商品の価格だけで送料無料になってしまいます。
ここも利益を生まない部分に繋がります。
しかしながら消費者の70%は送料無料の商品を選んで購入しているという傾向から、企業は送料無料のサービスをやめることができません。
やめたとたん競合企業にポジションを取られてしまいます。
こうした私たちの求めるサービスの過剰がやがて消費者自らの首をしめているということにそろそろ気づかなければなりませんね。
対応策
コンビニでの受け取り
近くのコンビニで24時間受け取りができるサービスです。
コンビニでは24時間店員がいるので受取人不在ということはありませんし、消費者も24時間取りに行くことが可能なので非常に便利です。
ただしコンビニも増える荷物に悲鳴をあげています。
自動受け取りボックス
自宅の前やマンションの入り口付近に「自動受け取りボックス」を設置し、在宅者がいなくても荷物を入れておけるようにします。
もちろんボックスには鍵がかかっていて、暗証番号で開く仕組みになっています。
受け取り可能カレンダー
受け取れる曜日と時間帯を個人で登録しておくことで、その時間に配達してくれるサービスです。
ネット通販のなかには時間帯指定ができないものも多く存在し、これこそが再配達を発生させる原因となっています。
この受け取り可能カレンダーがあることで受取人の在宅率があがり、再配達の回数を減らすことができると期待されています。
基本料金の引き上げ
ヤマト運輸では、配送の基本料金を100円引き上げを検討していると2017年3月7日に発表しました。
人件費を確保して人員を補充し問題解決を図ります。
再配達や時間指定サービスの見直し
運送会社の負担になっている再配達や時間指定のサービスを有料化するか時間変更するかの議論が現在行われています。
今までは規模拡大のためにサービスを無料で行ってきました。
それを今後は規模充実のため有料サービスに切り替えると私たちが解釈すればよいのです。
私はむしろその方が健全だと思います。
致し方なしといったところでしょうか。
自動運転システム
これはまだ実現化されていませんが、自動運転が完成した時には人手不足の解消に活用することが予測されます。
2020年代に訪れる自動運転に向けて、ヤマト運輸が2017年3月から実験をスタートするという発表もしています。
配達車が家の前まで自動で来るので、利用者はGPS信号でトラックの位置を確認して電話による通知を受け取り、自分で荷物を取りに行くシステムで検討しています。
中には高齢者の方の利用もあるので自分で取りにいけない人への考慮から、受取人が自動運転システムのサービスを利用するかどうかを選択するものと思われます。
ドローンでの宅配も検討されていますね。
これはまだまだ安全面での課題が多くありそうです。
さいごに
ネット通販の拡大により私たちの生活は便利になってきていますが、その一方で対応に追われる人々もいることは心に持っていなければなりません。
私の知り合いも皆口々にしていたのは、やはり「1回目の配達で受け取れない」ということです。
共働きが普通になった現代では、家に誰もいないことは当たり前です。
この問題を解決するために私たち消費者も理解と協力を行わなければなりませんね。





