【住民税】知らないと6月にビックリ!!
2018/03/30

今まで会社の給料から天引きされていた住民税は、個人事業主になると自分で支払いに行かなければなりません。
これを知らなかった場合は、いきなり家に支払い通知が来てビックリすることになりますね。
普通徴収と特別徴収
普通徴収
金融機関またはコンビニに行って振込用紙で支払う方法です。
個人事業主はこの支払い方法になります。
納付方法は「一括払い」と「4回払い」の2通りです。
6月に自宅に届く通知書と一緒に2通りの振込用紙が入っています。
どちらかを選択して支払いましょう。
特別徴収
会社から天引きされ支払われる方法です。
会社員、フリーターなどの従業員はこの支払方法です。
給料明細書を見ると住民税が引かれているのが分かると思います。
会社を辞めて独立した場合
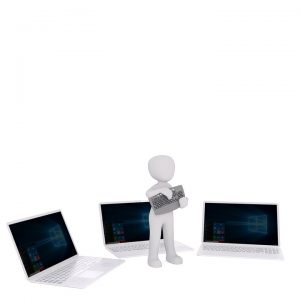
会社員やフリーターなどを辞めて個人事業主になる場合、これから自分で支払わなければならなくなります。
辞め方やタイミングによって支払い方が変わるので注意しましょう。
1月~5月に辞めた場合
辞めた後から5月分までが一括で給料天引きされます。
そのため最終月の給与は手取りが少なくなります。
たとえば3月で辞めた場合
通常の1ヶ月分+4月と5月の分=3ヶ月分
最終月で3ヶ月分が引かれます。
※給与の締日によって変わります。
また、給与が少なく金額が足りない場合は、残りの分は普通徴収になります。
不足分の納付書が後日自宅に届きます。
6月~12月に辞めた場合
一括で給与天引きするか普通徴収かを選択できます。
一括徴収を選択
来年5月までの分を一括で給与から天引きします。不足分は普通徴収になります。
普通徴収を選択
後日、納付書が自宅に届きます。
次の就職先を聞いてくる理由
次の会社で毎月天引きする場合は一括払いはありません。
会社を辞める際の面談で次の就職先を聞くのは、住民税の支払い方法を確かめる意味もあります。
昨年の収入に対して課せられる

確定申告で1年の所得が確定してから、6月に住民税が徴収されます。
したがって昨年の所得を基準にして支払っているということになります。
離職や転職などで収入が下がった人にとっては辛いものがあります。
たとえば1月に仕事を辞めた後、ずっと無職だったとしても6月になれば昨年の分の住民税の納付通知書が届きます。
これは昨年働いた分の税金のため、今年無職だったとしても必ず納税しなければなりません。
住民税の中身
住民税は所得割と均等割に分けられます。
均等割
住民税の納税者全員に均一に課せられます。
自治体によって金額は変わりますが、年間5000円~6000円くらいです。
所得割
所得に応じて金額が変化します。所得が上がるほど税率も上がるようになっています。
住民税が0円のケース

収入が少ない
無職あるいはフリーター、個人事業を開業して間もなくで1年間の収入が少なかった場合は住民税は徴収されません。
収入のボーダーラインは自治体によって変わりますが、たとえば東京都の場合は年収100万円以内であれば住民税は徴収されません。
生活保護を受けている
生活保護を受けている人へは住民税の徴収はありません。
その他
未成年者・障がい者・寡婦・寡夫で収入が少ない場合も徴収は免除されます。
個人事業主の場合
所得が125万円以下
従業員の場合
所得が204万4,000円未満
住民税の金額

「たいした金額じゃないんでしょ?」と甘く見ていると6月に通知書が来てビックリすることになります。
たとえば年収400万円だった人は19万円を支払うこともあります!!!
例)独身、年収400万円の場合
①年収400万円ー給与所得控除134万円=給与所得266万円
②266万円-基礎控除33万円ー社会保険料控除45万円=188万円
③課税対象188万円×住民税率10%=所得割18.8万円
④所得割18.8万円+均等割5000円=19.3万円
⑤19.3万円ー調整控除2500円=住民税190,500円
住民税として1年で190,500円を支払うことになります。
※本来は③で都道府県民税と市町村税を別々で計算しますが、ここでは合算して一緒にしています。
配偶者や扶養者の有無、生命保険の加入や医療費の支払い額などによって②の所得控除の額は変わります。
住民税は経費になる?

個人事業主は事業にかかった費用を経費に入れて税金対策を考えますが、住民税は経費にはなりません。
住民税は個人に対して課せられたものであるため、事業の費用とは認められません。





